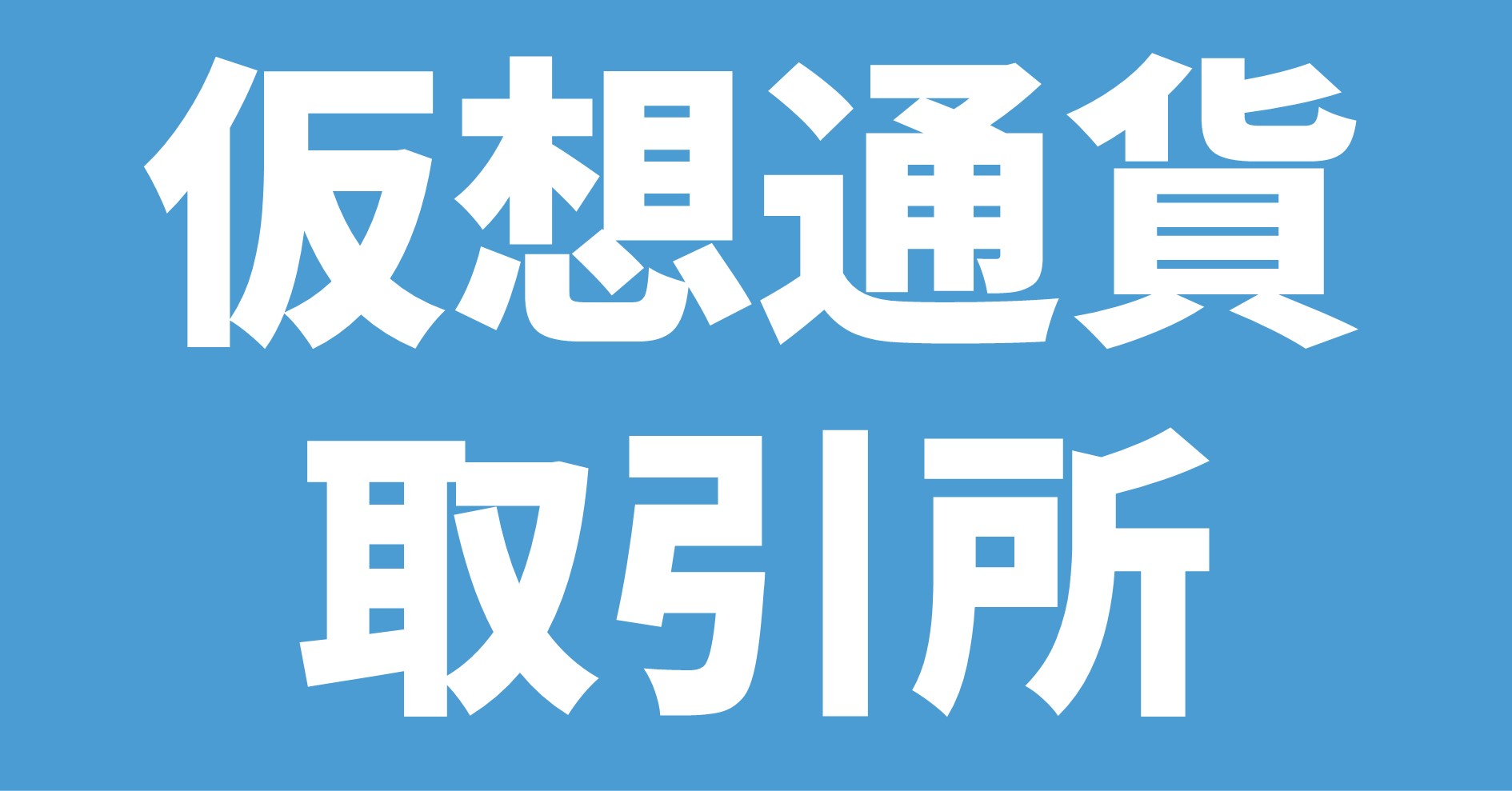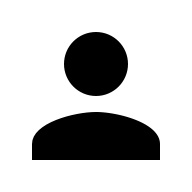
分散型サイエンスを教えて!
こういった悩みにお答えします.
本記事の信頼性
- リアルタイムシステムの研究歴12年.
- 東大教員の時に,英語でOS(Linuxカーネル)の授業.
- 2012年9月~2013年8月にアメリカのノースカロライナ大学チャペルヒル校(UNC)コンピュータサイエンス学部で客員研究員として勤務.C言語でリアルタイムLinuxの研究開発.
- プログラミング歴15年以上,習得している言語: C/C++,Python,Solidity/Vyper,Java,Ruby,Go,Rust,D,HTML/CSS/JS/PHP,MATLAB,Verse(UEFN), Assembler (x64,aarch64).
- 東大教員の時に,C++言語で開発した「LLVMコンパイラの拡張」,C言語で開発した独自のリアルタイムOS「Mcube Kernel」をGitHubにオープンソースとして公開.
- 2020年1月~現在はアメリカのノースカロライナ州チャペルヒルにあるGuarantee Happiness LLCのCTOとしてECサイト開発やWeb/SNSマーケティングの業務.2022年6月~現在はアメリカのノースカロライナ州チャペルヒルにあるJapanese Tar Heel, Inc.のCEO兼CTO.
- 最近は自然言語処理AIとイーサリアムに関する有益な情報発信や,Unreal Editor for Fortnite(UEFN)でゲーム開発に従事.
- (AI全般を含む)自然言語処理AIの論文の日本語訳や,AIチャットボット(ChatGPT,Auto-GPT,Gemini(旧Bard)など)の記事を50本以上執筆.アメリカのサンフランシスコ(広義のシリコンバレー)の会社でChatGPT/Geminiを訓練するプロンプトエンジニア・マネージャー・Quality Assurance(QA)の業務委託の経験あり.
- (スマートコントラクトのプログラミングを含む)イーサリアムや仮想通貨全般の記事を200本以上執筆.イギリスのロンドンの会社で仮想通貨の英語の記事を日本語に翻訳する業務委託の経験あり.
- UEFNで10本以上のゲームを開発し,フォートナイト上で公開(Fortnite,Fortnite.GG).
こういった私から学べます.
仮想通貨を取引したいあなたは,まずは国内取引所のCoincheckを開設しましょう!
Coincheckが扱っていない仮想通貨を取引したい場合や低い手数料で取引したい場合は,海外取引所を開設する必要があります.
しかし,海外取引所は日本円が使えないので,国内取引所から仮想通貨を送る必要があります.
そこで,以下のおすすめの仮想通貨取引所(主に海外)で開設して,Coincheckからビットコインやイーサリアムを送りましょう!
目次
分散型サイエンス(DeSci:Decentralized Science)
分散型サイエンス(DeSci:Decentralized Science)とは,Web3.0スタックを用いて,科学的知識の資金調達,作成,レビュー,クレジット付与,保存,普及のための公共インフラを公正かつ公平に構築することを目的としたムーブメントです.
DeSciの目的は,科学者が研究をオープンに共有し,誰でも簡単に研究にアクセスし,貢献できるようにしながら,その研究に対する恩恵を受けるようなエコシステムを構築することです.
DeSciの活動理念は,科学的知識は誰もがアクセスできるべきであり,科学的研究のプロセスは透明であるべきだという考えです.
DeSciは,より分散化された分散型科学研究モデルを構築し,中央当局による検閲や管理に対して耐性を持たせています.
また,DeSciは,資金,科学ツール,コミュニケーションチャネルへのアクセスを分散化することで,新しい型破りなアイデアが花開く環境を作りたいと考えています.
DeSciは,より多様な資金源(DAO,二次寄付,クラウドファンディング等),よりアクセスしやすいデータや手法,そして再現性のためのインセンティブを提供することによって,より多くの資金を得ることができます.
DeSciの解説動画はこちらがわかりやすいです.
DeSciと従来のサイエンスの比較
DeSciと従来のサイエンスの比較は下表になります.
DeSciが実現すると,研究者に大きなメリットがあることがわかります.
私の経験から言うと論文の査読はとても大変なので,正当な報酬が得られると嬉しいですね!
| 項目 | DeSci(Web3.0) | 従来のサイエンス(Web2.0) |
|---|---|---|
| 資金の分配 | 資金の分配は,二次寄付やDAOなどの仕組みを用いて,パブリックに決定. | 小さく閉じた中央集権的なグループが,資金の分配をコントロール. |
| 協力関係 | 世界中の仲間とダイナミックなチームで協力. | 資金提供団体や所属機関により,共同研究が制限. |
| 資金調達 | 資金調達の決定は,オンラインかつ透明性をもって実行.新しい資金調達の仕組みが検討. | 資金調達の決定は,長いターンアラウンドタイムと限られた透明性で実行.資金調達の仕組みがほぼない. |
| 研究所のリソースの共有 | Web3.0のプリミティブを利用することで,研究所のリソースをより簡単に,より透過的に共有可能. | 研究所のリソースの共有は,しばしば時間がかかり,不透明な可能性があり. |
| 論文の出版 | 信頼性,透明性,普遍的なアクセスのためのWeb3.0プリミティブを使用する出版のための新しいモデルを開発可能. | 非効率的,偏見的,搾取的と言われる確立された経路を経て出版. |
| 論文の査読 | 論文を査読することでトークン(仮想通貨)とレピュテーション(評判)を得ることが可能. | あなたの論文を査読する作業は無報酬で,営利目的の出版社に利益を提供. |
| 知的財産の所有権 | 自分が作成した知的財産(IP)を所有し,透明性のある条件に従って配布可能. | あなたの所属する機関が,あなたが生成したIPを所有.IPへのアクセスは不透明. |
| 研究の共有 | すべてのステップをオンチェーンにすることで,失敗したデータも含め,すべての研究を共有可能. | 出版バイアスは,研究者が成功した実験を共有する傾向があることを意味する. |
DeSciとイーサリアム
DeSciには,堅牢なセキュリティ,最小限の金銭および取引コスト,そしてアプリケーション開発のための豊富なエコシステムが必要です.
イーサリアムは,DeSciスタックの構築に必要なすべてを提供します.
イーサリアムを知りたいあなたはこちらからどうぞ.
DeSciのメリット
DeSciのメリットは以下になります.
- 高い信頼性と透明性:DeSciでは,複数の研究者や専門家がデータセットや解析手法にアクセスし,独自の分析や検証を行います.これにより,研究結果や科学的な主張の信頼性が向上し,透明性が確保され,研究の再現性も高まります.
- 大規模なデータセットの活用:DeSciは,複数のデータソースやデータベースを活用することができます.これにより,より大規模なデータセットを扱い,多様な情報源からの洞察を得ることができ,より包括的な分析や洞察が可能になります.
- イノベーションの促進:DeSciは,より広範な人々が参加し,知識やアイデアを共有できる環境を提供します.これにより,異なるバックグラウンドや専門分野の人々が協力し,新たな発見やイノベーションが生まれる可能性が高まります.
- リスクの分散:従来の中央集権的なアプローチでは,一部の研究者や機関に大きな責任とリスクが集中します.しかし,DeSciでは,複数の参加者がデータや解析に関与するため,リスクが分散されます.これにより,シングルポイントの障害やエラーによる影響を軽減することができます.
DeSciのユースケース
DeSciのユースケースは以下になります.
- 分散型データ共有とコラボレーション:DeSciは,研究者やデータサイエンティストがデータを共有し,協力して研究を進めるためのプラットフォームを提供します.これにより,異なる地域や組織のデータを統合的に利用することができます.
- 分散型コンピューティング:DeSciでは,複数のコンピュータやデバイスをネットワーク上で結合し,処理能力や計算リソースを分散して活用します.これにより,大規模なデータセットや複雑な計算を高速かつ効率的に処理することができます.
- ブロックチェーン技術を活用した信頼性の向上:DeSciでは,ブロックチェーン技術を使用してデータや解析の透明性と信頼性を確保します.ブロックチェーンは,データの改ざんや不正アクセスを防ぐための分散型のデータベースとして機能し,研究の信頼性を高めます.
- 分散型マーケットプレイス:DeSciのコンセプトは,データやアルゴリズムの共有を通じて,研究者やデータサイエンティストが相互に取引できるマーケットプレイスの形成にも適用されます.これにより,データや解析手法の利用者と提供者が効果的につながり,共同の成果を生み出すことが可能になります.
DeSciのコミュニティ
DeSciのコミュニティは以下になります.
興味があるコミュニティに参加してみましょう!
- Active Inference Lab
- Atoms
- Bio.xyz
- DeSci Foundation
- DeSci.World
- Fleming Protocol
- OceanDAO
- ResearchHub
- VitaDAO
まとめ
分散型サイエンス(DeSci:Decentralized Science)を紹介しました.
DeSciが実現すると,科学者にとって大きなメリットがあることがわかりました.
仮想通貨を取引したいあなたは,まずは国内取引所のCoincheckを開設しましょう!
Coincheckが扱っていない仮想通貨を取引したい場合や低い手数料で取引したい場合は,海外取引所を開設する必要があります.
しかし,海外取引所は日本円が使えないので,国内取引所から仮想通貨を送る必要があります.
そこで,以下のおすすめの仮想通貨取引所(主に海外)で開設して,Coincheckからビットコインやイーサリアムを送りましょう!